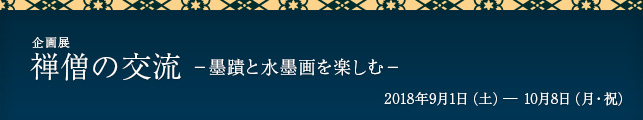
独特な書風の墨蹟と、画僧による水墨画から禅僧の日中交流を眺める
中世に、中国へと渡った日本人留学僧や、日本に招かれた中国僧達はそれぞれに現地の禅僧と交流を深めます。その様子は独特な書風で書かれた墨蹟や、水墨画などに描かれました。高僧の遺徳がしのばれる品として大切に伝えられてきた作品から、当時の交流の様子を眺める企画展です。
臨済宗の開祖である
本展では、賛が付された水墨画や、尺牘、墨蹟など、約50件を展示。
| 展覧会名 | 企画展 「禅僧の交流−墨蹟と水墨画を楽しむ−」 |
|---|---|
| 会期 | 2018年9月1日(土) 〜 10月8日(月・祝) |
| 休館日 | 月曜日(ただし9月17日、9月24日は開館)、9月18日(火)、9月25日(火) |
| 時間 | 10:00〜17:00 ※入館は閉館時間の30分前まで |
| 会場 | 根津美術館 港区南青山6-5-1 >> 会場の紹介記事はこちら |
| 入館料 | 一般 1,100円、高大生 800円 |
| 公式サイト | http://www.nezu-muse.or.jp/ |
| 問合せ | 03-3400-2536 |
記載内容は取材もしくは更新時の情報によるものです。商品の価格や取扱い・営業時間の変更等がございます。