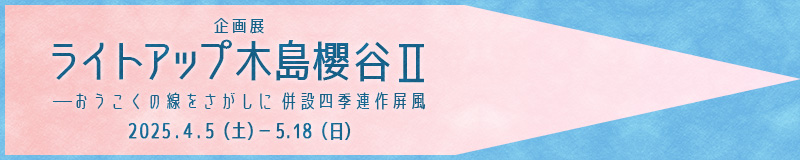
櫻谷の人物画に光をあて
多彩な表情をもつ線の美しさに浸る
大正中期に大阪・天王寺の茶臼山に建てられた住友家の本邸を飾るため、
本展では特に、《かりくら》や《唐美人》をはじめとする櫻谷の人物画にスポットをあてるとともに、櫻谷の写生帖をいつもより増量して展示し、櫻谷の線描の妙を探訪する。
京都の三条室町の商家に生まれた木島櫻谷(1877~1938年)は、円山・四条派の流れをくむ今尾景年に入門する一方、儒学者で本草学者の山本渓愚(章夫)にも師事し、漢籍などを学んだ。
2つの伝統を踏まえながら新時代の感性を取り入れた画風により、若くして人気を博した。20代半ばには京都の展覧会で例年入賞するようになり、京都画壇を担う人材として文展・帝展で活躍した。
櫻谷は写生について、「写生とは何度も繰り返し実物に接し、そのイメージを頭に留めるためのもので、たとえ写生帖が手もとになくても、ありありとその姿を思い浮かべられるようにならなければいけない」と語り、600冊を超える数の写生帖類を遺している。
「1.櫻谷の写生帖、なんども繰り返し写した線の軌跡。」の章では、大量に遺された櫻谷の写生帖をいつもより増量して並べ、櫻谷が対象をどのように捉え、写し取ろうとしたのか、その線の軌跡をたどる。
櫻谷が絵を学びはじめた頃の京都では、なによりも運筆が重視され、師の手本をもとに徹底した修練が行われた。そうした環境のなかで磨かれた櫻谷の運筆。そこから生み出される線は、実に多彩な表情を持ち、対象のかたちを写し出すことはもちろん、その存在感や息づかい、ときには感情までも描き出している。
「2. 息遣い、感情、存在感…、櫻谷の線は語る。」では、そのような線による表現が駆使された人物画にスポットをあて、櫻谷作品における線の妙を紹介する。
住友家の十五代当主・住友吉左衞門友純(号・春翠、1864~1926年)が大正中期に造営した邸宅を飾るため、櫻谷に依頼されたのが四季連作屏風の制作であった。
「3. 線がおりなすハーモニー、住友家本邸を飾った四季連作屏風。」では、線もまた、本作の見どころのひとつとなる様子を紹介。柳の枝や葉がおりなす曲線、燕子花の葉が描く軌道など、櫻谷の線の妙は、花木図においても健在である。
写生する線のスピード感と臨場感、本画には息の長い繊細な線からフリーハンドによる粗放ながら的確な線まで、息を飲むほど美しい櫻谷の線をさがしに足を運んでみてはいかがだろうか。



| 展覧会名 | 企画展 ライトアップ木島櫻谷Ⅱ―おうこくの線をさがしに 併設四季連作屏風 |
|---|---|
| 会期 | 2025年4月5日(土)~5月18日(日) |
| 休館日 | 月曜日(5月5日・6日は開館)、5月7日(水) |
| 時間 | 11:00~18:00(金曜日は19:00まで) ※入館は閉館時間の30分前まで |
| 会場 | 泉屋博古館東京 港区六本木1-5-1 >> 会場の紹介記事はこちら |
| 入館料 | 一般 1,200円、高大生 600円、18歳以下無料 |
| 公式サイト | https://sen-oku.or.jp/tokyo/ |
| 問合せ | 050-5541-8600 (ハローダイヤル) |
記載内容は取材もしくは更新時の情報によるものです。商品の価格や取扱い・営業時間の変更等がございます。