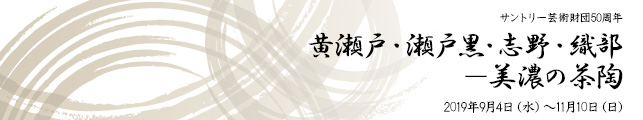
桃山時代に生まれた茶陶・美濃焼の、造形の魅力と評価の高まりを追う
茶の湯のためのやきもの「茶陶」が日本各地の窯で創造された桃山時代、岐阜県の美濃(東濃地域)では、力強い姿、鮮やかな色、斬新な意匠をもつ茶陶「黄瀬戸・瀬戸黒・志野・織部」が大量に焼かれ、おおいに流行した。そして、近代数寄者、目利き、陶芸家、古陶磁研究家などがそれぞれの立場から活発に古陶磁を蒐集・研究し、やきものを愛する彼らにとって、美濃焼は憧れの存在になっていった。
本展では、その個性的で生き生きとした造形の魅力に触れ、さらに近代数寄者旧蔵の名品や、近代陶芸家の荒川豊蔵と加藤唐九郎の代表作を通じて、近代以降の美濃焼の人気や評価の高まりを紹介する。
第一章では、「姿を借りる」「描く」「歪む」「型から生まれる」などのキーワードを手がかりに、黄瀬戸・瀬戸黒・志野・織部の造形の魅力を探る。美濃焼には、桃山時代までに日本で珍重された中国陶磁・古銅器・漆工品などさまざまな茶道具の姿を象ったと思われる作品があるが、決してその忠実な模倣ではない、新しい茶陶の姿を見ることができる。また、桃山時代の和物茶陶の中でも、美濃焼はとても多様な方法で加飾を試みており、とりわけ、鉄を絵具とし釉下に筆で描く「鉄絵」の技法は、陶器を蒔絵や染織にならぶ華やかな装いへと導いた。一方、桃山時代の和物茶陶に共通して現れた美意識が「歪み」で、茶陶一点一点に力強さと個性を与えるのに重要な役割を担っている。さらに、ろくろ成形後の素地やタタラ(粘土板)を型に押し当て器を形作る「型打」の技術は、大量生産を実現したのみならず、器を円形や円筒形から解放し、自由な造形を実現する画期的な技術であった。このように、美濃焼独特の造形やその時代の潮流から生み出された、多彩な鉢や蓋物、向付がキーワードに沿って展示される。
第二章では、近代以降高い評価と人気を得るようになった美濃焼の復興の様子を、美濃古陶の研究に熱心に取り組み自らの表現へと昇華させた陶芸家、荒川豊蔵と加藤唐九郎の代表的な作品と、潤沢な資金を以て名品の茶道具を蒐集し、独自の茶風を築いた近代数寄者のコレクションから追う。
※会期終了に伴い画像を削除いたしました| 展覧会名 | サントリー芸術財団50周年 黄瀬戸・瀬戸黒・志野・織部 −美濃の茶陶 |
|---|---|
| 会期 | 2019年9月4日(水) 〜 11月10日(日) |
| 休館日 | 火曜日(11月5日は18:00まで開館) |
| 時間 | 10:00〜18:00 ※金・土曜日および、9月15日(日)・22日(日)、10月13日(日)、11月3日(日)は20:00まで ※入館は各閉館時間の30分前まで |
| 会場 | サントリー美術館 港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア3階 >> 会場の紹介記事はこちら |
| 入館料 | 一般 1,300円、高大生 1,000円、中学生以下無料 |
| 公式サイト | https://www.suntory.co.jp/sma/ |
| 問合せ | 03-3479-8600 |
記載内容は取材もしくは更新時の情報によるものです。商品の価格や取扱い・営業時間の変更等がございます。